幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿
読者対象:
出版年月:
ページ数:164



――「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」とは?――
平成29年3月に改訂・改定された、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に、新たに示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」。今次改訂の最大のキーワードであると言っても、過言ではないでしょう。「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、新しい小学校学習指導要領でも記載され、低学年のすべての教科において、この10の姿との関連を図ることが示されています。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
① 健康な心と体
② 自立心
③ 協同性
④ 道徳性・規範意識の芽生え
⑤ 社会生活との関わり
⑥ 思考力の芽生え
⑦ 自然との関わり・生命尊重
⑧ 数量や図形、文字や標識などへの関心・感覚
⑨ 言葉による伝え合い
⑩ 豊かな感性と表現
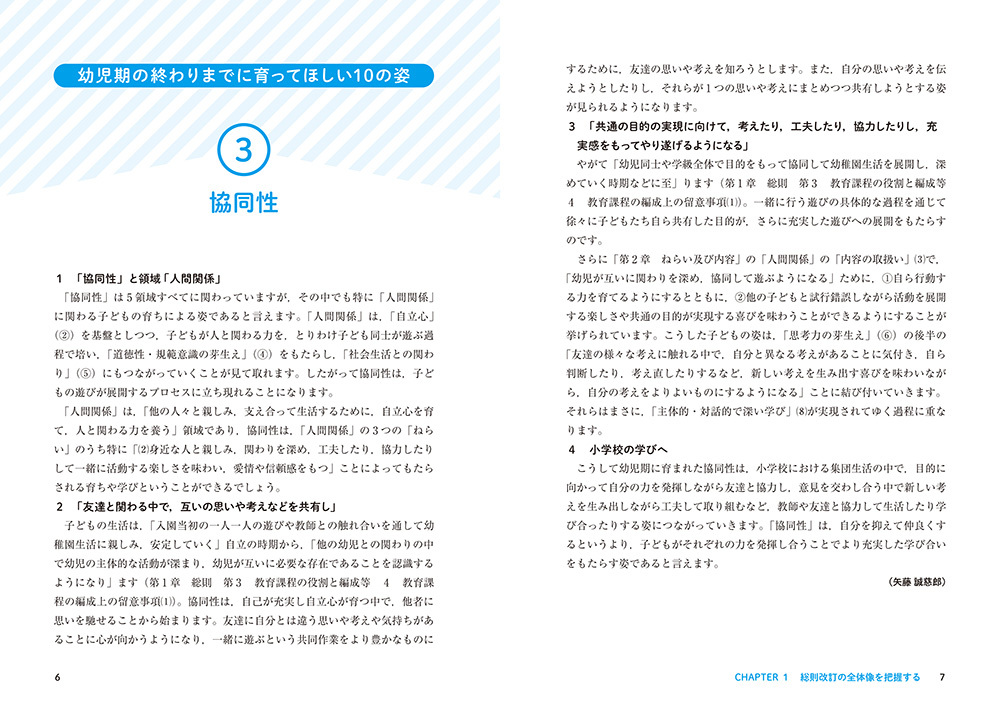

――10の姿を意識することのメリット――
幼稚園においては、「ねらい」及び「内容」に基づく活動全体を通して資質・能力が育まれていきますが、その中の5 歳児後半に育まれてくる姿を10にまとめたものが「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」です。幼稚園においては、幼児の発達や学びの個人差に留意しつつ、幼児期の終わりまでに育ってほしい幼児の姿を具体的にイメージして、日々の保育を行っていく必要があります。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を考慮することで、幼児をあらためてよく見るようになったり、重要な幼児の学びや発達の姿を偏りなく見ることができるようになったりします。また、入園から修了まで、長い見通しで子どもの姿を理解できるようになるでしょう。
幼稚園と小学校の教師が、「幼稚園教育において育みたい資質・能力」や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」等を理解することによって、接続期の子供像が共有され、より滑らかに接続ができるようになるでしょう。

――10の姿をイメージしながら日々の保育を行う――
実践においては、10の姿を個別に取り出し保育を行ったり、10の姿のみに力点を置いて保育を行ったり、幼児期の終わりの到達目標として幼児の育ちを評価したりするものではないということを基本に置くことが大切です。指導に当たっては、10の姿がどのように育まれているかという過程こそが大切にされなければなりません。本書では、事例においてもその過程から、どのような姿が育っているかを、分かりやすく紹介しています。
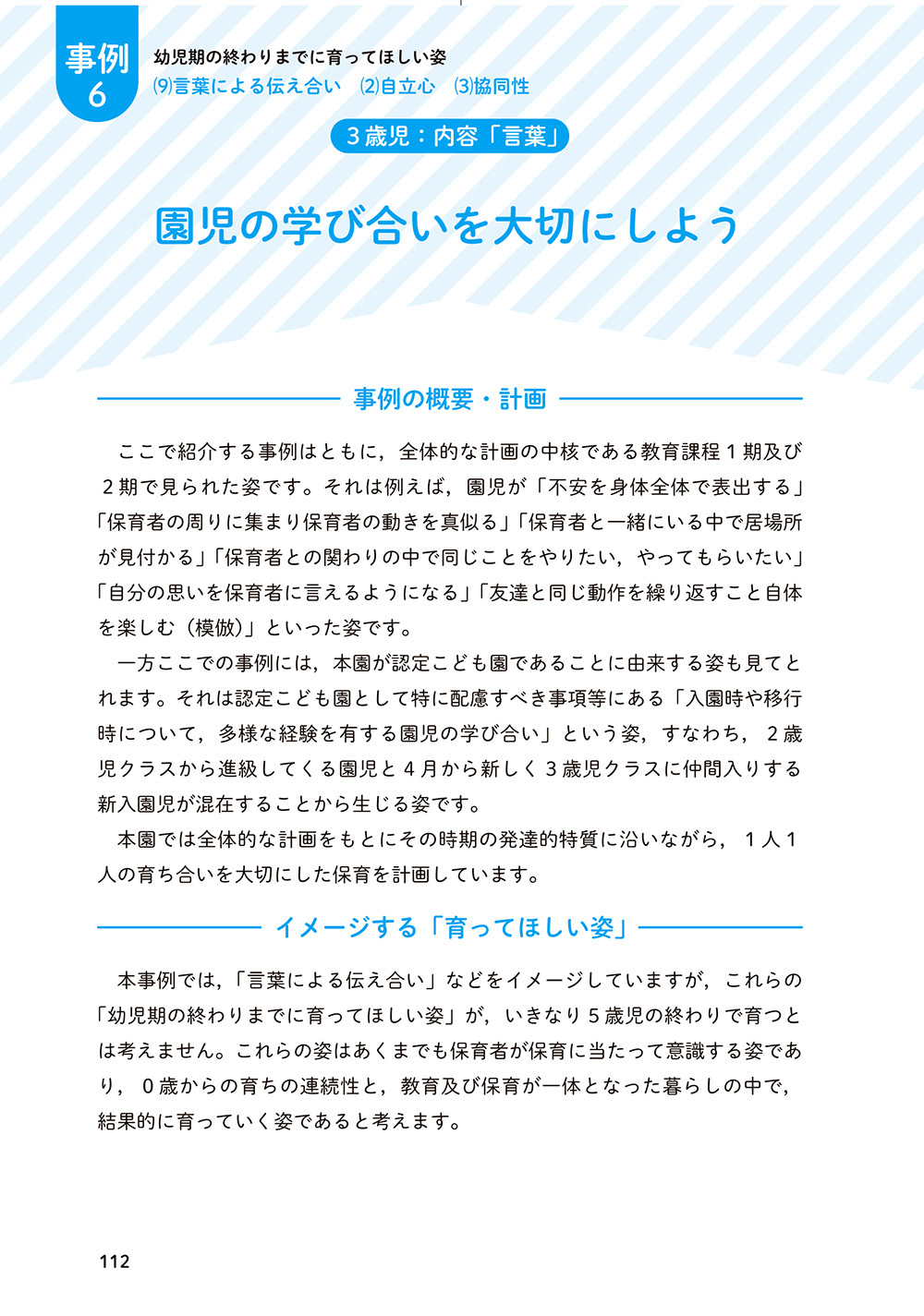
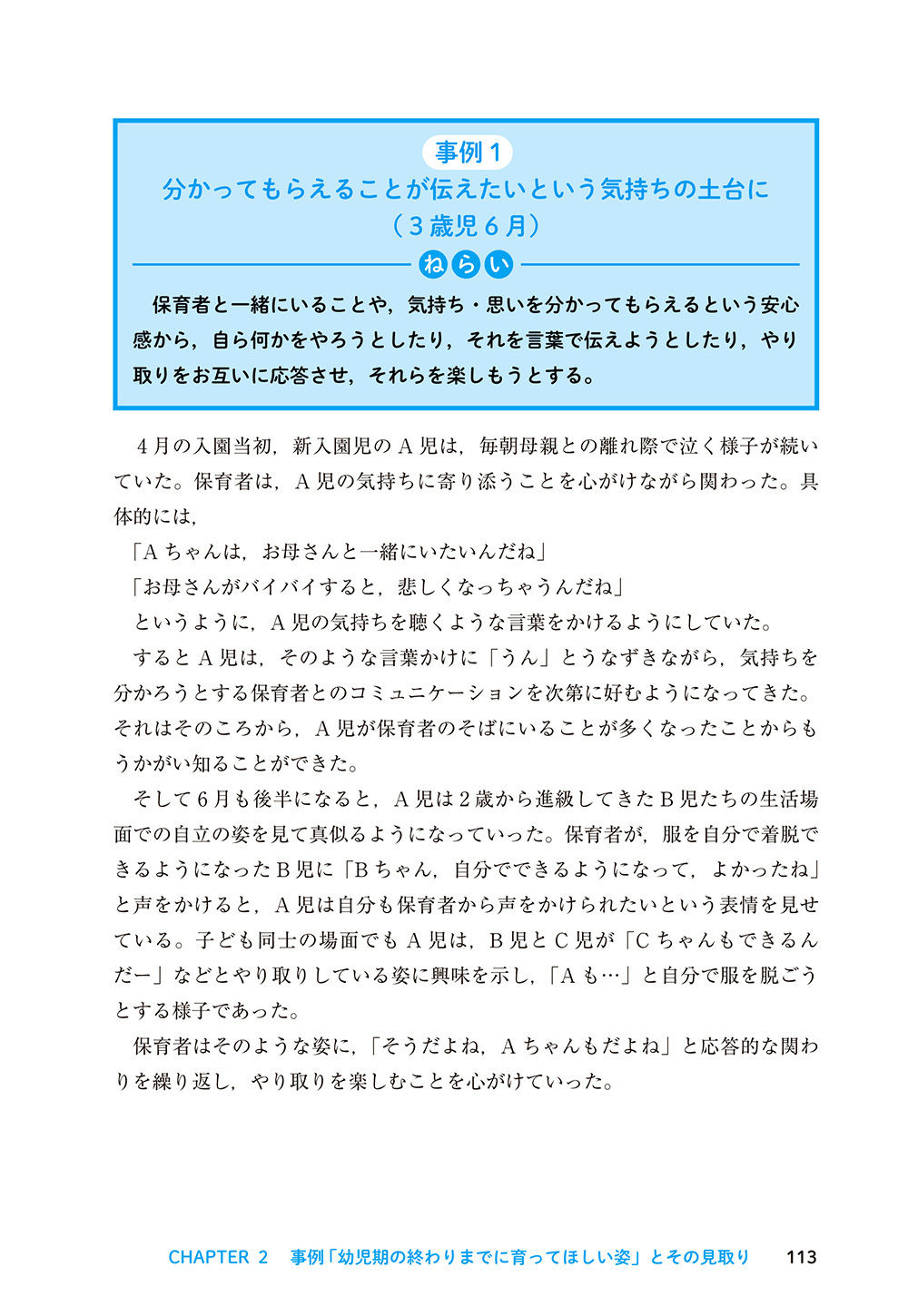
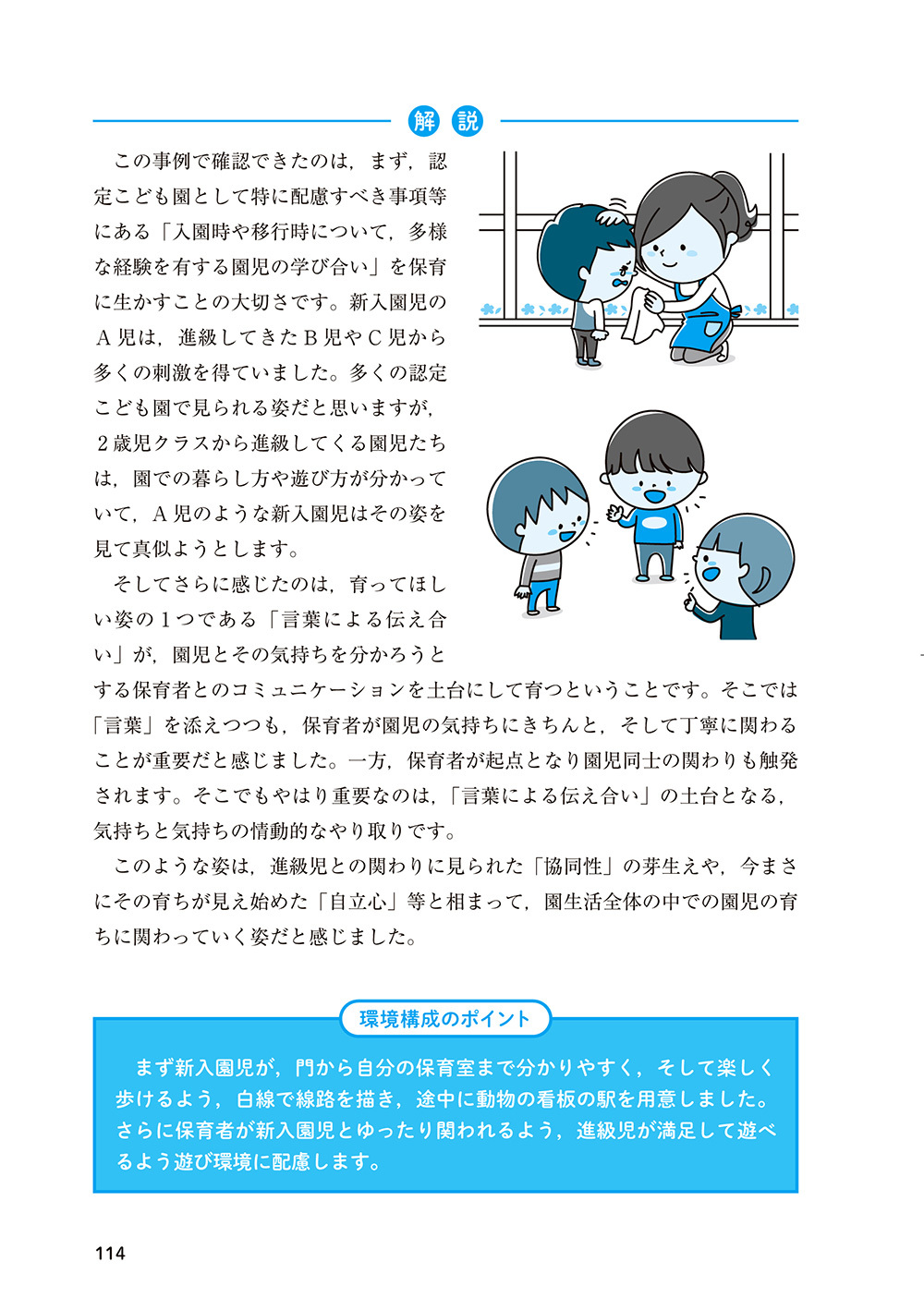
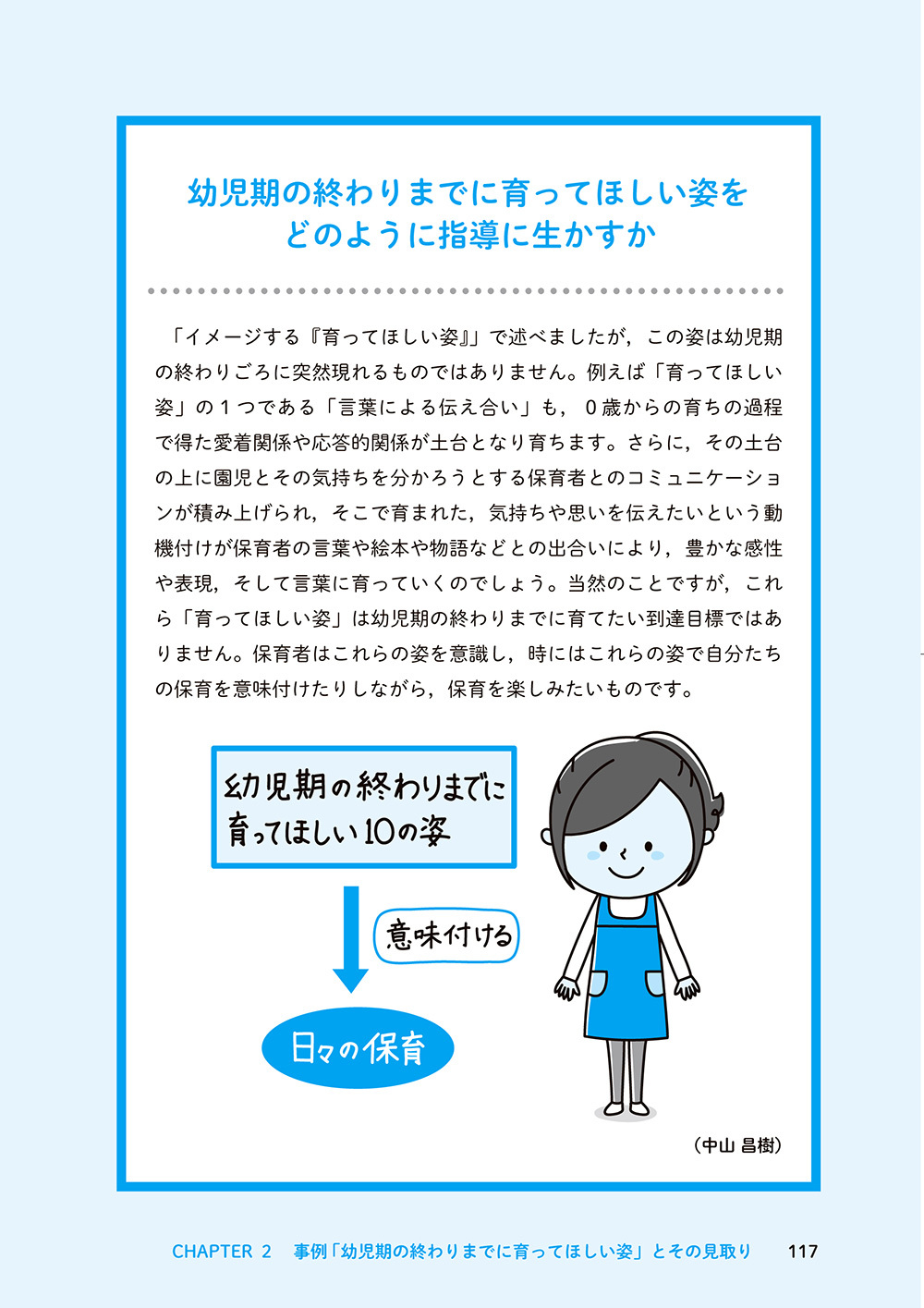
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が丸わかり!
![新しい幼児教育のキーワード 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」って何? 本書を読めば、その答えが分かります! ■3歳児未満/3歳児/4歳児/5歳児/小学校1年 豊富な13事例を紹介! 幼稚園教育要領、保育所保育指針等の改訂・改定のキーマンである、 無藤隆先生監修! 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿 無藤隆[編著]](https://images.benchmarkemail.com/client658114/image5503210.jpg)
目次 Contents
幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿
PROLOGUE 今後の幼児教育とは 1
第1章 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿とは 9
生まれた瞬間から始まる0歳児からの教育 10
これからの1歳、2歳の保育の在り方を考える 14
これからの幼児教育の在り方を考える 18
乳幼児期の子どもの教育の在り方とは 22
幼児期において育みたい資質・能力とは 26
幼児期にはどのような見方・考え方があるのか 30
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿とは 34
幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿
?健康な心と体 38
?自立心 40
?協同性 42
?道徳性・規範意識の芽生え 44
?社会生活との関わり 46
?思考力の芽生え 48
?自然との関わり・生命尊重 50
?数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 52
?言葉による伝え合い 54
?豊かな感性と表現 56
幼児期における「主体的・対話的で深い学び」の姿とは 58
幼稚園におけるカリキュラム・マネジメントとは 62
幼小接続とスタートカリキュラム 66
全体的な計画の作成の重要性
Column 1
保護者等に「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」についてどのように共通理解を図るか 74
第2章 事例 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿とその見取り 77
実践する上で,「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をどう意識していくか 78
事例1 3歳児未満 自分で気付き興味をもとう,納得いくまで探究しよう 82
事例2 3歳児未満 何だろう,不思議さの入り口 88
事例3 3歳児未満 イメージを身体や言葉で表現しよう 94
事例4 3歳児 友達と創り出す遊びの楽しさ 100
事例5 3歳児 安心して社会と触れ合う基礎となる体験を 106
事例6 3歳児 園児の学び合いを大切にしよう 112
事例7 4歳児 気付きを大切にし,自身をもって粘り強くやってみよう 118
事例8 4歳児 連続した遊びの中で「思考力の芽生え」を培う 124
事例9 4歳児 やりたいことに向かって繰り返し取り組む 130
事例10 5歳児 何個食べたのかな? 数えてみよう 136
事例11 5歳児 中当てをやってみよう! 142
事例12 小学校1年 「がっこうたんけん」 148
事例13 小学校1年 スタートカリキュラムから学校探検へ 154
Column 2





